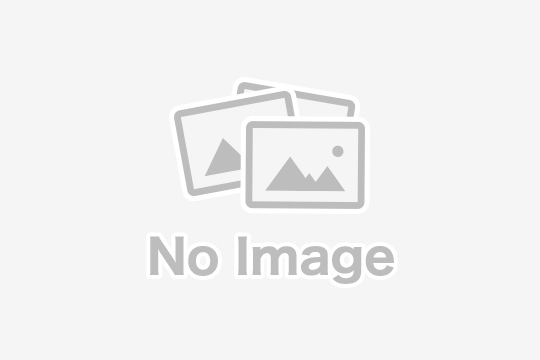この記事は約 5 分で読めます。
こんにちは、めしラボです。
鉄フライパンの扱いに慣れていないと「食材がくっついてしまって調理にならない」という経験をされる方は少なくありません。私もそうでした。食材がくっついてしまうのには明確な理由がありますので、まずは理屈を知ることが大切です。
ここでは食材がくっついてしまう仕組みとくっつかせないポイントを説明していきます。
 めしラボ
めしラボ今回の記事は次のような人におすすめ!
- 鉄フライパンに食材がくっついてしまって調理にならない。
- 食材がくっついてしまう仕組みを知りたい。
- 鉄フライパンにくっつかないようにするにはどうすればよいのか?
鉄フライパンは油切れにより食材がくっつきます。
油切れの原因として多いのが「間違った使い方をしてしまっている」「油膜の形成が不十分」「鉄フライパンの選び方(主に厚さ)に問題がある」「熱ムラのある状態で使い始めている」などです。鉄フライパンはフッ素樹脂加工のフライパンとは大きく異なりますので注意が必要です。
また食材の温度が影響してしまうこともあります。
スポンサーリンク
鉄フライパンの使い方とは?
鉄フライパンは油切れを起こさせないように使うことがポイントになります。
鉄フライパンは「から焼きをして温めてから油を引く」「温度のムラができる場合には油返しをする」「肉や魚などは表面が焼き固まるまで動かさない」などのポイントがありますが、これらのポイントには明確な理由があります。
フッ素樹脂加工のフライパンに慣れていると驚くはずです。
| 温めてから油を引く | 油なじみが良くなる |
|---|---|
| 油返しをする | 熱ムラが解消される |
| 焼き固まるまで動かさない | 球状たんぱく質の活性基によりくっつきやすい |
また、油の使用量は食材により変化します。
たとえば動物性たんぱく質の食材(肉や魚など)は付着力が高いために多く必要ですが、卵は付着力が弱いために少なくて済みます。ケーキや芋のようなでんぷん質の食品の場合には金属面を油で拭く程度でも問題なく調理できます。
ちなみに油慣れしていない鉄フライパンの場合には1.5倍ほどの油を必要とします。
鉄フライパンの油膜の形成とは?
鉄フライパンは油膜により食材の凝着を防ぎます。
鉄フライパンにはノンスティックフライパンのような表面コーティングがありませんので、油を酸化重合させることにより形成される油膜(樹脂皮膜)により食材が金属面に直接触れないようにしています。油膜が形成されてない鉄フライパンは油切れを起こしやすいためにくっつきやすくなります。
特に注意してほしいのが動物性のたんぱく質です。
肉や魚(動物性たんぱく質)を鉄フライパンで焼くと筋形質たんぱく質の球状たんぱく質が熱凝固する過程で一時的に活性基を露出させます。活性基が露出しているタイミングで金属面に触れていると金属と結びついてしまうためにくっついてしまいます。
油膜が形成されていれば金属への付着を防ぐことができます。
鉄フライパンの選び方とは?
鉄フライパンの選び方は厚さ(重さ)がポイントになります。
食材の焦げつきやすさには鍋材質の熱伝導率と厚さが深くかかわっています。基本的に熱伝導率が高いほど、鍋底が厚いほどに焦げつきにくくなります。誤解されている方も多いかと思いますが、鉄の熱伝導率はお世辞にも良いものではありません。
以下の表は熱伝導率の比較です。
| 熱伝導率 W/(m・K) | |
|---|---|
| 銅 | 398.0 |
| アルミニウム | 237.0 |
| 鉄 | 80.3 |
| ステンレス SUS405 | 27.0 |
ステンレスが焦げつきやすいのは熱伝導率が低いためです。
これらのことからも肉や魚を焼くための鉄フライパンは「厚みのあるもの(重いもの)」を選ぶことがポイントになります。これは鉄の熱伝導率の悪さをカバーするためには熱容量(比熱×質量)を高くするのが効果的であるためです。
場合によってはスキレットも選択肢に入ります。
一般的な鉄フライパンの板厚は2mm前後ですが、スキレットの板厚は4mm前後となります。また鉄フライパンは鋼鉄をプレスもしくは打ち出しで作られているのとは違い、スキレットは鋳鉄(鋳造)で作られているために表面には無数の穴が開いています。
そのため「食材がくっつきにくい」という特徴を持ちます。
食材を常温に戻す理由は?
食材を常温に戻しておくとくっつきにくくなります。
冷蔵庫から出したばかりの食材は5℃前後に冷えています。薄切り肉などであれば問題はありませんが、ステーキなどのように厚みのある肉の場合には鉄フライパンの熱を奪ってしまうためにくっつきやすくなります。特に板厚の薄い鉄フライパンの場合には注意が必要です。
急激に温度が下がりますので、生焼けやうま味の流出にもつながります。
目玉焼きの中央がくっつきやすいのもこのためです。冷蔵庫から出したばかりの卵で目玉焼きを作ると、卵黄の部分が大きく熱を奪うためにくっつきやすくなります。また家庭用ガスコンロには安全センサー(Siセンサー)がついていますので「熱ムラができやすい」というデメリットもあります。
そのため可能であれば「食材は常温に戻しておく」「熱ムラができてしまう場合には油返しをしてから使い始める」などがポイントになります。
まとめ・鉄フライパンがくっつく理由は?
鉄フライパンは油切れによりくっつきやすくなります。
そのため「油なじみをよくするために温めてから油を引く」「油膜が不十分な場合はくず野菜を炒めるなどして鉄フライパン育てていく」「調理に合わせた板厚の鉄フライパンを選ぶ」「厚切り肉などは常温に戻してから調理をする」などがポイントになります。
ノンスティックフライパンの扱いとは大きく異なりますので注意が必要です。
おすすめの関連アイテム
厚板フライパン 極(リバーライト)
- 材質:
- 鉄(特殊熱処理)
- 板厚:
- 3.2mm
- 重量:
- 0.83kg
リバーライトの厚板タイプです。
特殊熱処理(窒化処理)が施されていることに加え「3.2mmの厚板仕様になっている(通常タイプは1.6mm)」「木製のハンドルが採用されている」などの特徴があります。これにより「耐摩耗性や耐食性に優れる」「酸化皮膜を形成させる必要がない」「熱容量が高いことにより料理の仕上がりが良くなる」「ハンドルが熱くならない」などのメリットが得られます。
管理人のレビュー
特殊熱加工が施されていることに加え「一般家庭の台所においても違和感のないデザイン」が気になっています。現在使用している鉄フライパンはデバイヤーですが、機会があれば使いたい(切り替えたい)と考えています。
IH対応鉄フライパン(デバイヤー)
- 材質:
- 鉄
- 板厚:
- 2.5mm
- 重量:
- 1.38kg
デバイヤーの定番鉄フライパンです。
盛り付けをしやすいハンドル角度とデザインの良さが魅力の鉄フライパンです。高品質な厚板の鉄が使われていることもあり、安価な鉄フライパンと比べると格段に使いやすい(食材がくっつきにくくサビにくい)仕様になっています。
管理人のレビュー
デザインの良さが気に入って使っています。しかしデバイヤーの特徴ともいえるハンドル角度には「蓋が干渉してしまう」というデメリットもあります。お使いの蓋の流用を考えている場合には注意が必要です。
打出し 鉄 フライパン(山田工業所)
- 材質:
- 鉄(打ち出し)
- 板厚:
- 2.3mm
- 重量:
- 1.25kg
山田工業所の定番フライパンです。
通常の鉄フライパンはプレス(圧力を加えて成型する方法)などで作られていますが、山田工業所の鉄フライパンは打ち出し(たたいて成形する方法)で作られています。これにより鉄の分子が詰まり、硬く粘りのある性質を持つようになります。
管理人のレビュー
機能性を重視するのであれば山田工業所の打出し鉄フライパン一択かと思います。事実、多くの飲食店では山田工業所の鉄フライパンや中華鍋が好まれています。デザインが好みで台所の印象と合うのであれば心からおすすめできます。
竹ささら(遠藤商事)
- 材質:
- 竹
- 長さ:
- 235mm
- 重量:
- 105g
中華鍋に用いられることの多い竹ブラシです。
家庭での鉄フライパンの洗浄には少し長めに感じられるかもしれませんが、熱を持ったまま洗うことの多い鉄フライパンの洗浄では少し長めくらいの方が使いやすいです。気兼ねなく使える価格帯であることからもおすすめできます。
管理人のレビュー
一般的な竹ささらです。そのままでは硬く洗いにくいことからも「10分ほど煮る」「束ねられている部分に瞬間接着剤をしみ込ませる」「先端を剪定鋏などで斜めにカットする」などをして扱いやすくすることをおすすめします。
フライパン洗い ブラシ(マーナ)
- 材質:
- 馬毛
- 長さ:
- 25cm
- 重量:
- 80g
柔らかい馬毛のブラシです。
馬毛は耐熱・耐薬品性に優れているため、表面を傷つけることなく優しく洗い上げることができます。鉄フライパンを洗うには心もとなく感じられるかもしれませんが、ある程度育っているフライパンに洗剤を付けて洗う場合にはおすすめできます。
管理人のレビュー
鉄フライパンの扱いに慣れていない場合には竹ささらをおすすめします。しかしほとんど焦げ付かせることがなく育ってきた油膜を傷つけないように洗いたい場合などには重宝します。ある程度の油慣れをしているフライパンであれば洗剤で洗っても問題ありません。
超強力マグネットフック(Sendida)
- 材質:
- ステンレス鋼
- 耐荷重(垂直方向):
- 10kg
- 耐荷重(水平方向):
- 7kg
強力なマグネットフックです。
フック部分の回転する強力マグネットフックですので、溝やつなぎ目の少ないタイプのレンジフードでも鉄フライパンなどを吊るす(かける)ことができます。耐荷重は「垂直方向10kg」「水平方向7kg」ですので厚板の鉄フライパンであっても安心です。
管理人のレビュー
レンジフードには溝のあるタイプ(ブーツ型)と溝のないタイプ(スリム型)の2種類があります。ブーツ型の場合は溝に掛けるタイプのフックを使えますが、スリム型の場合には超強力なマグネットタイプのフックがおすすめです。